インタビュー
そうぎょう 執行役員 岡崎 克彦 氏
- 投稿日時
- 2025/06/26 09:14
- 更新日時
- 2025/06/26 09:17
切削油リユース製品をリブランド
そうぎょうと言えば「オイルスキマー」を思い浮かべる人は多い。同社は環境ハードウエアに注力しており、オイルスキマ―はもちろん切粉処理装置の伸長を目指す。その拡販の指揮を執る執行役員エコエネ部部長の岡崎克彦氏に話を聞いた。
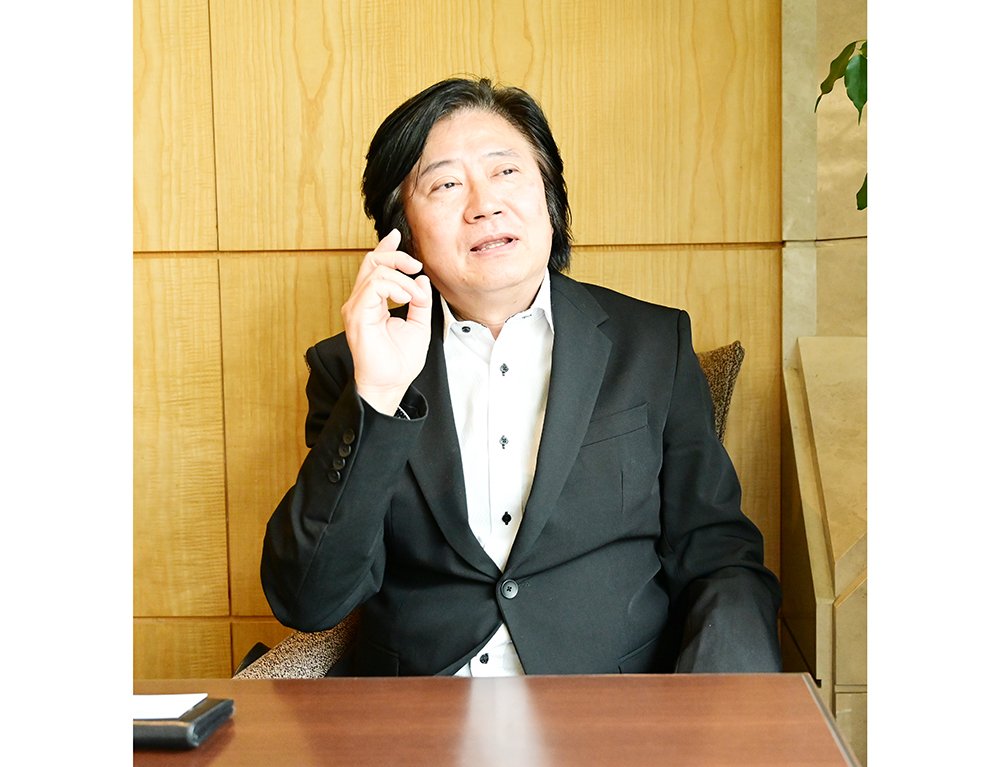
そうぎょう執行役員 エコエネ部部長・岡崎克彦氏
――貴社の簡単な紹介をお願いします。
「そうぎょうには2つの事業部門があり、その中心は自動車から家電・食器など生活のあらゆるシーンで使用されている製品(ファインメッシュ・ファインラス・スピーカーグリルなど)を自動車業界をはじめ幅広く販売しており、この事業が売上の大半を支えています。私がマネージメントをしているのが環境ハードウエア部門です。私は4年近く前、グループ会社の自動車部門から環境ハードウエアを伸長させるミッションを担って転籍してきました。これまではそうぎょうと言えば『オイルスキマー(浮上油回収装置)』が代名詞になっていたのではないでしょうか」
――オイルスキマーは安定した市場ですが、急速な伸長は難しいのでは。
「そうですね。今は伸長の可能性を秘めた切粉処理装置の商品群の伸長を目指しています。金属加工業者から排出される金属切屑から切削油と混合物を分離し、油をリユースする脱油機。その高精度脱油システム『エコロアース』などが代表商品です」

高精度脱油システム『エコロアース』
――エコロアースのコア技術は。
「『自動・連続・定量』の脱油フローにより高精度に混合物から切削油を分離します。もう少し具体的に言うとバケットの高速回転による遠心力で内部に投入された定量の切屑から、バケット内のスリットで切削油を切屑から分離します。この工程を自動かつ連続で繰り返すところに独自のコア技術があります」
「ただ切粉処理装置自体は決して新しいテクノロジーではなく、商社や販売代理店に話を持っていっても、新鮮味がなく、当初は思うように広がっていきませんでした」
――リブランドが必要ですね。
「カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミーなどがトレンドワードとなり、行政も力を入れています。愛知県環境局を訪ね相談を持ち掛けると、大企業は環境対策が進んでいるが中小企業はまだまだ油のリユースなども進んでいない。県の循環ビジネス創出コーディネーターの方々からも助言いただきながら、愛知環境賞に応募。昨年、優秀賞を頂きました。この動きを全国に広げるため令和6年度 資源循環技術・システム表彰にも応募し産業環境管理協会会長賞も頂けました」
――今年3月に愛知県環境局が後援した『加工機周辺の資源循環・環境対策展』にも主体的にかかわられた。
「当社だけではなく前工程・後工程含め、様々な環境機器メーカーで協力して何かできないかと考え、機械商社『山善』にいろいろ相談にいき、イベント化しました。同展示会に参加した企業との協業話なども出て来ており、将来的には寄合化して定期的な会合を開きつつ、いつか共同開発なども出来ればと思っています」
「実は環境対策のトレンド(廃プラ、繊維衣類、食品、木材など)において『金属と油』というのは、決して新たな取り組みとして環境改善の活動を進めているマテリアルではありません。しかしながら、『金属と油』も実質、取り組まれているのは大手企業が中心で、特に愛知県下を幅広く裾野で支えている中小企業においてはまだまだ環境改善への取り組みが積極的に進んでいないんです。そこに商機もあると思っており『加工機周辺』というくくりで企業連携や商社との連携を通じて、資源循環推進に向けた活動と環境ハードウエアにおけるビジネス戦略を両輪で進めて行かなければならない」
――生産効率を上げる装置ではないので、中小企業では後回しになりますね。
「現場での設備導入の説明や最適な環境への提案が順調に運んでも、一方で経営層による決済で『これ生産効率上がらないから、今じゃないでしょ?』と時期見送りや案件消滅になりがちでした。現在は現場での案件導入検討と同時進行で、経営層へ投資効果の説明を進めております。つまり切削油のリユースによる購入費削減と脱油処理することで切屑の引き取り価格上昇ですね。ケースバイケースですが、原料価格の高騰で現在は1年半ぐらいで投資回収できる場合もありますよ。更に循環型社会形成に向けたサーキュラーエコノミー及び脱炭素社会に向けたカーボンニュートラルの活動に結び付く効果が得られます」
(日本物流新聞2025年6月25日号掲載)





