オピニオン
日本歯車工業会 専務理事 宇都木 崇 氏
- 投稿日時
- 2025/07/28 09:00
- 更新日時
- 2025/07/28 09:10
5月の総会で新たに副会長2人を選出し、会長1人、副会長3人の新体制とした(一社)日本歯車工業会。今まで以上に会員の声に耳を傾け「メンバーファースト」を大切にする。国際競争力強化を意識し、今年度はホームページを多言語化しての情報発信力も高めるという。
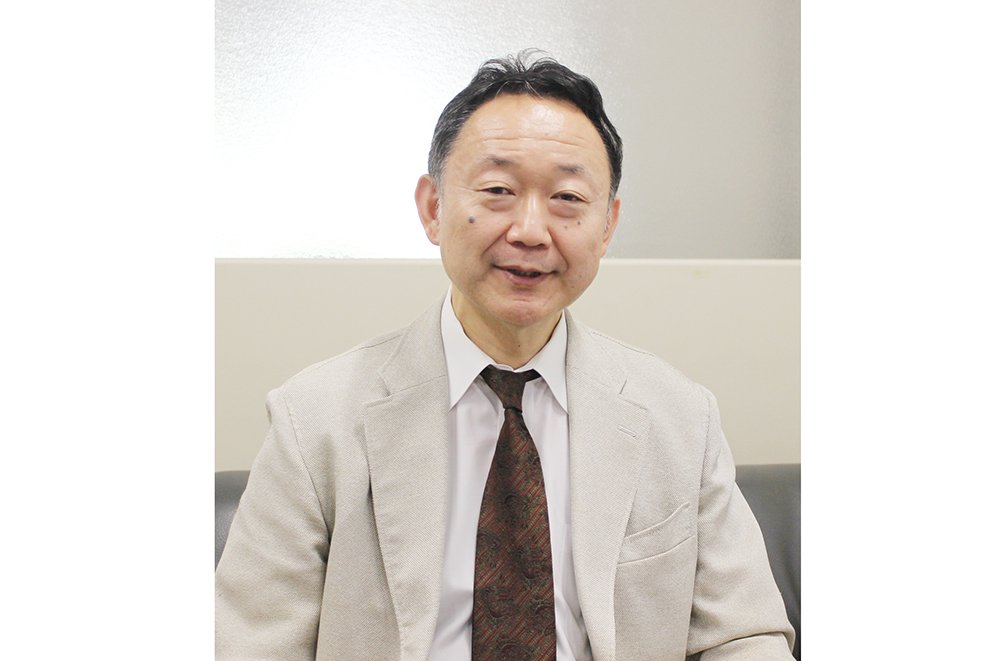
グリーソンの営業職を定年退職し、2024年3月に現職に就いた宇都木崇専務理事。18歳で米国に渡り、大学を卒業し大学院修士課程を修了した。メーカー勤務時代には競合だった企業を会員として迎え入れようと意欲を燃やす。
——加工機メーカーの動きを見ると歯車加工の重要性が再認識されているようです。業界の景況感は。
「当工業会は121社の会員で構成されます(2025年3月末現在)。このうち正会員の歯車加工会社が88社、賛助会員の加工機・測定機メーカーが33社。9割は中小企業で、コロナ禍を経て自動車関係の仕事をもつ会員は少なくなりました。正会員の半数ほどのデータを取りまとめた年間売上高は近年、2800億〜3800億円(非歯車製品を含む)で推移してきました。2023年度は前年度比2割増、24年度は同8%増という実績です」
「近年は業界の再編、後継者問題による廃業などで会員数は少し減りました。でもその一方で、若い社長を迎え新しい分野に挑戦しようとする意欲的な会社が入会されています。たとえば航空機や自動車分野の試作をする会社は、ホブを使わずに独自開発のソフトとストレートの1枚刃でインボリュート曲線に仕上げたりします」
——貴工業会は会長1人、副会長3人の新体制とされました。狙いは。
「会長は菊地歯車(栃木県足利市)の菊地義典社長、副会長はオージック(大阪府東大阪市)の田中文彦会長、長岡歯車製作所(新潟県長岡市)の加納孝樹社長、ナゴヤギア(愛知県名古屋市)の藤島忠康社長の3名です。当工業会の理事会などのイベントは東京で開くことが多くありました。大阪や神戸で催すこともありましたが、東京一辺倒にならないように関東、大阪、名古屋に副会長を置いて多くの会員の参加を促したり、会員各社の声を聞いていこうというのが狙いです。と同時に幹部の若返りも図っています」
——歯車技術全般を学べる対面講義の「ギヤカレッジ(歯車技術講座)」(今年6月から来年2月)をスタートされました。受講者は集まりましたか。
「マスターコース(基礎講座)には定員の30名が、プロフェッショナルコース(応用講座)には16名(定員20名)が受講しています。嬉しいことに、前回のマスターコース受講者のうち10名がプロフェッショナルコースを受講されています。この講座の定着と技術レベルのスムーズな向上が期待できます。実はプロフェッショナルコースはこれまで1ケタの受講者数という年も珍しくありませんでした。内容を充実させたりPRに力を入れたことで、去年も19名と多くの方に受講いただけるようになりました」
——どんな内容ですか。
「私も去年参加させていただきましたが、昔とは違うギヤのつくり方、特に5軸マシニングセンタ(MC)で歯車をつくる動きがあって、それを大手工作機械メーカーさんで学ぶ特別講座も含まれます。またどんなソフトを使うと有効か、どんな機上測定ができるか、3次元測定機で測定した結果を5軸MCにフィードバックするような講座も新しく加えています」
——秋には海外視察を企画されています。
「11月23〜30日にドイツ、スイスの企業を視察します。歯車加工・測定の巨人と言われる企業を片っ端から見てこようと。当工業会は伝統的にはEMOハノーバーやシカゴショーに行くことが多かったのですが、その時期は宿泊費が高騰しフライトも混みます。また当会の会員はすべての加工機を見たいわけではなく、主に歯車加工機を見たいという希望があります。そこで訪問先としてカップ・ナイルス、クリンゲルンベルグ、グリーソンファウター、リープヘル、ライスハウアーの5社を選びました。できれば若い人に参加してもらい、最高級加工機の工場を見たもらいたい。一度に名門5社を見る機会はまずないと思います」
——今年は力が入りますね。想定される参加人数は。
「20名の参加が目標です。日本で高精度な歯車をつくるために一番輸入されている機械はやはり歯研盤ですから、まずはそれを中心にしっかり見たいと考えています。昨年韓国へ行った際も20名弱で、歯車メーカーを中心に工具メーカーや見本市も視察しました。同業他社を見ると、韓国はいまどれくらいの技術レベルなのか、どんな工夫をしているのかを学べます。その前の年は台湾の歯車メーカーを中心に見て回りました。来年以降は年ごとにテーマを変えて、たとえば測定機メーカーを中心に回るとか、工具メーカーを中心に据えるとか、材料メーカーに焦点を当てるとか。そんなふうに考えています」
一般社団法人日本歯車工業会
1938年設立、会員121社(2025年3月末現在)
東京都港区芝公園3-5-8
東京歯車製造工業組合として設立。2013年に一般社団法人に移行した。正会員(歯車メーカー)88社と賛助会員(加工機・測定機メーカー)33社で構成する。コロナ禍を経て自動車分野大手の賛助会員は減ったが、一方で若い社長を迎え新しいい分野に挑戦しようとする意欲的な企業が入会。ギヤについて体系的に教える大学が少なくなるなか、九州大学大学院が産官学連携事業として2005年に設置した「ものづくりスーパー中核人材センター」(08年からは九州大学の自立事業として「ものづくり工学教育研究センター」に改称)のなかの「歯車製造コース」を11年に継承し「ギヤカレッジ」として主催する。国際交流、教育、規格の3事業を基本軸とする。
(日本物流新聞2025年7月25日号掲載)





