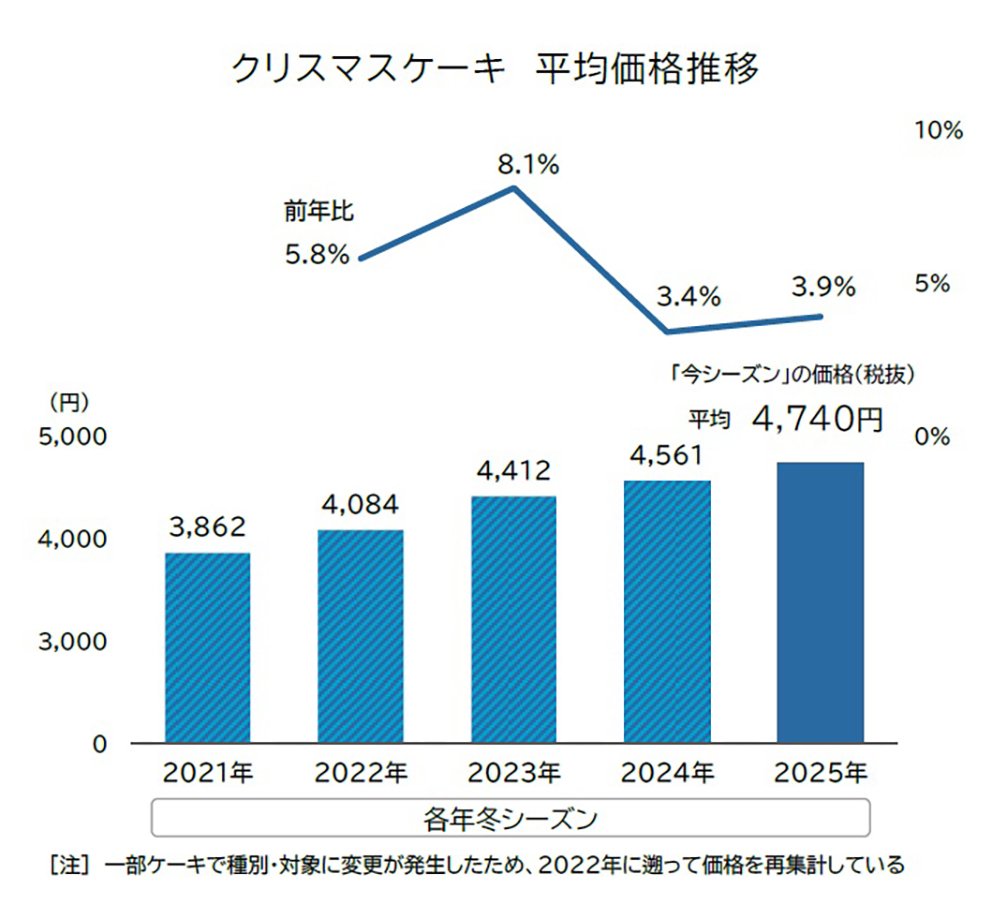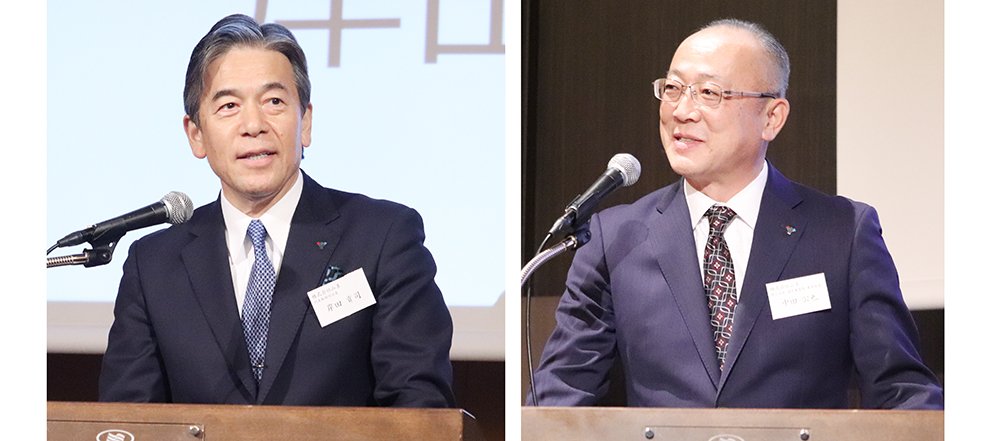「あなたなら何を入れる?」中学生が考える「防災バッグ+1」の備え
- 投稿日時
- 2025/08/11 09:00
- 更新日時
- 2025/08/08 09:41

松蔭中学校
家族写真?折り畳み傘?それとも雪平鍋?――災害時に本当に必要な1アイテムは何か。阪神・淡路大震災の被災地にある松蔭中学校(兵庫県神戸市)ではユニークな防災授業が展開されている。累計販売数200万セットを記録する山善の「防災バッグ30」を教材に、バッグに「もし何か一つ足すなら」を考えプレゼンテーションする。2021年から行われているこの授業には毎年、多彩なアイデアが発表される。授業を考えた同校の篠原弘樹先生に話を聞いた。
「防災バッグに、あなたなら何を足しますか?」
阪神・淡路大震災の発災から30年を迎えた兵庫県神戸市にある松蔭中学校では毎年2月、山善の「防災バッグ30」を活用した授業が行われる。
携帯トイレや懐中電灯、非常用給水バッグなど、一時避難に必要な30点のアイテムが詰め込まれたこのバッグを、同校のグローバル・ストリームコース1年の生徒たちが手に取り、どんな状況でどうやって使うか体験する。そして「バッグにもう1つアイテムを加えるなら何か?」をテーマに、1人ひとりが独自のアイデアを考え提案する。
ある生徒は「晴雨兼用折り畳み傘」を選んだ。「雨や日光をしのげる」ことに加えて、「(避難所などで)プライベートを確保できる」点がポイントだという。また別の生徒は「家族写真」を挙げた。「家族写真は見ているだけで安心できて、家族とはぐれた時に探すのも役立つ」という。他にも「浮き輪」「雪平鍋」など、発想は多彩だ。
単にアイデアを出すだけではない。授業の目的は「なぜそれを選んだのか」を論理的に言語化し、自分の言葉で表現することにもある。プレゼンテーションに加えて、実際の活用シーンをイメージした小説も執筆する。人間関係や心情を想像しながら描き出すことで、備えの本質や実感に迫る。特に、小説化は、自分の中で被災した状況を想像し整理しなければ言語化できないため、災害や防災を自然と「自分ごと化」しやすいという。

生徒たちのアイデア資料。資料も生徒たちが自作する
授業を企画、実施した篠原弘樹先生は次のように語る。
「被災地にある当校としては、この時期には震災に関する授業を行いたい。一方で、生徒たちは既に様々な形で学習してきている。加えて、震災を経験していない世代の学生です。どうやったら実感を持って、主体的に防災や災害に意識を向けられるかを意識しました」
生徒たちが考えたアイデアは、防災バッグ30を開発した山善 家庭機器事業部 商品企画4部の小浜成章部長(防災士)のもとに届けられ、開発者目線のコメントがフィードバックされる。

本授業を考案した松蔭中学校 グローバル・ストリームコースの篠原弘樹先生。大学でも教えた経験からくる実践的な英語の授業に生徒から高い評価を得ている
「プロから意見がもらえることは生徒にとっても貴重な機会。今年は小浜部長に当校にお越しいただき、その場でフィードバックいただきました。生徒たちがいつも以上に熱心に耳を傾ける姿が印象的でした」
篠原先生は、学習の定着を図るため、高校でもう一度同じ授業を行いたいと話す。「中学校で基本的な考え方を学んだ後に、子どもたちがどのように災害と向き合うのかに非常に興味があります」
年齢や性別などそれぞれの立場によって災害への向き合い方は大きく異なる。十分な備えをしていたからといって、被災時にはその備えに手が届くとは限らない。「阪神・淡路大震災」「東日本大震災」――どこか距離のある災害に主体的に向き合った経験が、すべてが足りない被災地で活きてきそうだ。
山善 家庭機器事業部 商品企画4部 小浜 成章 部長
「篠原先生から生徒たちのアイデアが送られて来たときは、商品コンセプトと同じ発想の授業が行われていると知り大変おどろきました。今では毎年、アイデアが届くのを楽しみにしています。学生たちならではのユニークで自由な意見が見られ、商品開発の参考にもさせていただいています。特に印象に残っているのは『家族写真』です。我々、開発者の視点ではなかなか思いつかないアイデアなので」
(日本物流新聞2025年8月10日号掲載)