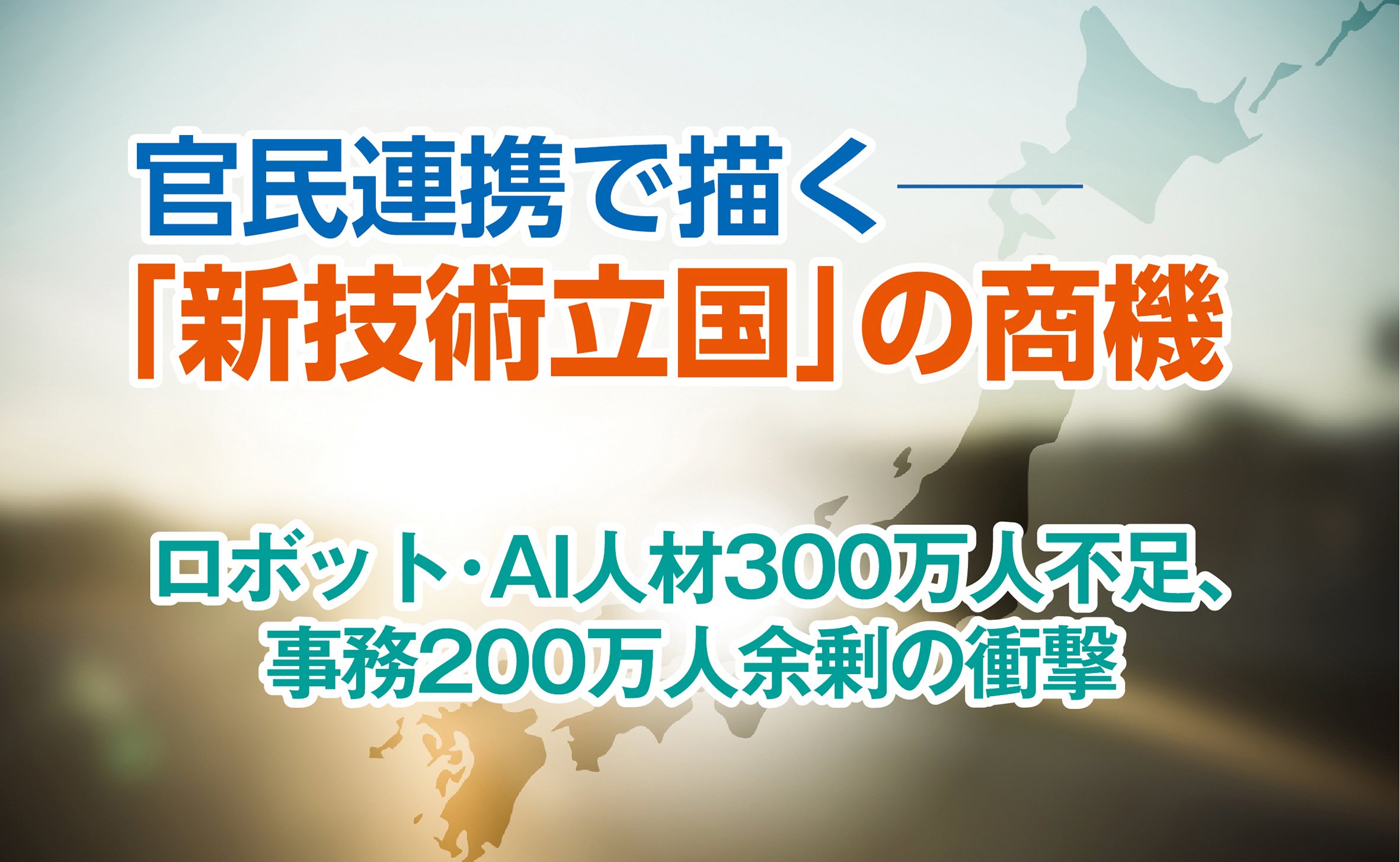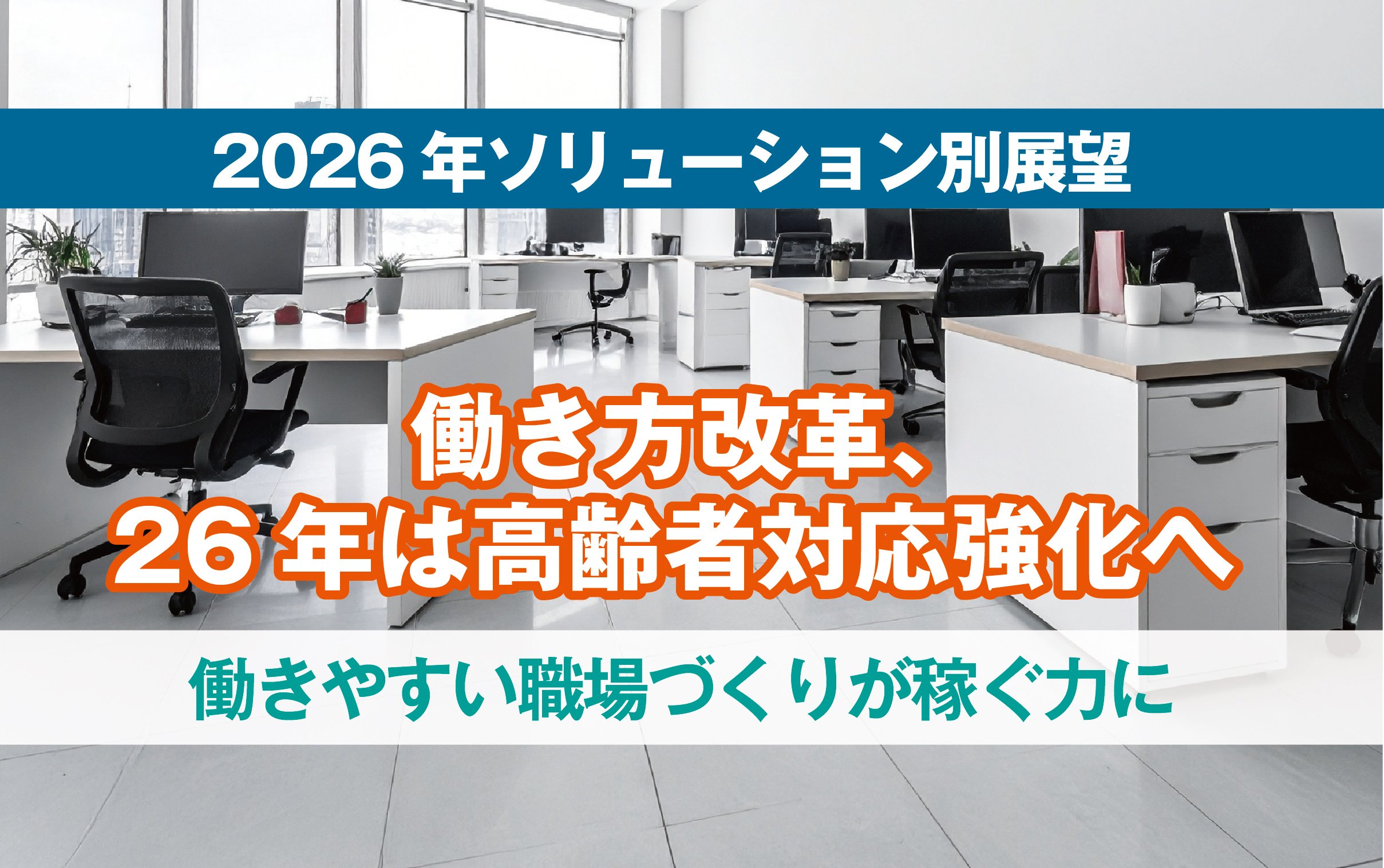万博「終幕」から始まる未来への序章
- 投稿日時
- 2025/10/02 10:58
- 更新日時
- 2025/10/02 11:15
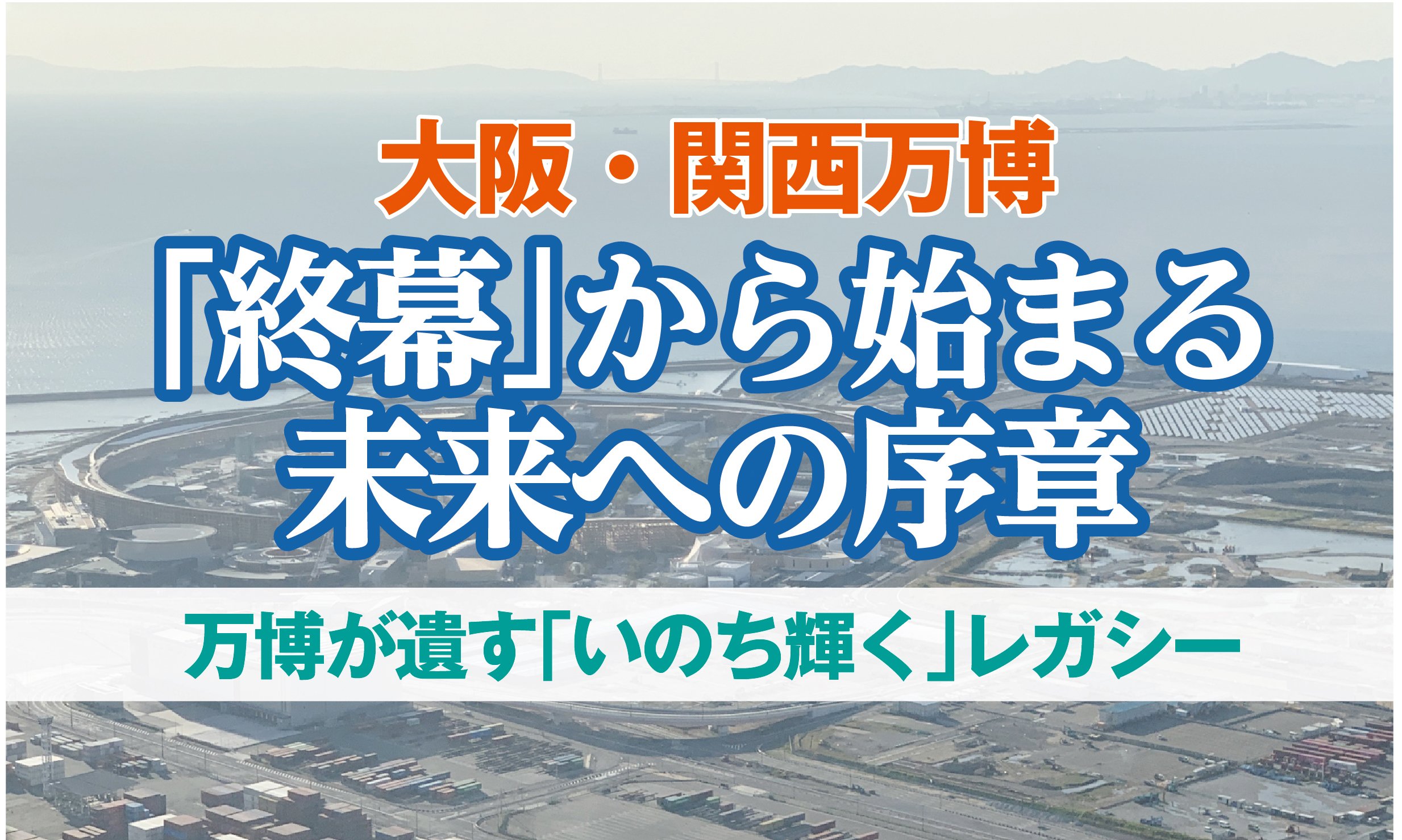
大阪・関西万博が遺す「いのち輝く」レガシー
9月18日時点で累計2000万人を超える来場者で賑わった大阪・関西万博が、10月13日、いよいよそのフィナーレを迎える。経済効果は2・9兆円とも言われ、人々の心を躍らせた一大イベント。だが、この熱狂を一過性のものに終わらせてはならない。万博が掲げた「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現するため、私たちは何をすべきなのか。本特集では、会期中に披露された先進技術の中から、社会実装へと続く「レガシーのシード(種)」となりうる技術を徹底取材。夢洲で生まれた未来への道筋をたどる。
大阪ラセン管工業/大阪ヘルスケアパビリオン
出展期間10月7日~13日
「柔らかい金属」が生む可能性、VR空間で没入
人気パビリオンの一つとして来館者数400万人(9月6日時点)を突破している大阪ヘルスケアパビリオン。大阪の中小企業やスタートアップの技術力を伝えるリボーンチャレンジでは6カ月間に及んだ万博のフィナーレに相応しく、10月7~13日まで健康やSDGsにまつわる未来技術が結集し、万博のテーマである「いのち」を感じられるテクノロジーが集う。
目玉は1912年創業の日本最古となるフレキシブルチューブとベローズのメーカー、大阪ラセン管工業(大阪市西淀川区)による最先端の「柔らかい金属」がもたらす未来の可能性だ。

画像はVR空間ブースのイメージ図。写真内の展示品より、さらに径が細いフレキシブルチューブを初披露する
フレキシブルチューブとは気密性のある金属製配管でありながら、ゴムチューブのように自在に曲げて使用することができる金属製チューブ。水道やガス配管のインフラから半導体製造装置の真空配管まで幅広く使われるが、蛇腹形状で金属の成型加工を伴うため極細化は技術的に難しく、一般的に内径3㍉メートル程度が最小径。そのため医療分野で求められる極細径チューブは樹脂製チューブが一般的となっている。しかし「管が細くなるほど、医療分野での用途が広がり、技術革新に繋がる」と考えた小泉星児社長は径1・0㍉メートル以下の「超極細フレキシブルチューブ」を開発。ガイディングカテーテルなどで使われる樹脂製チューブよりも耐久性が上がり、チューブの破れなどの課題も解決できる。万博のテーマの一つ「いのちを救う」を実現する超極細フレキシブルチューブは技術の粋を集める。
■畳める金属製ベローズ
金属製ベローズは伸縮させて使える蛇腹形状の金属製配管。従来は力を加えて縮めても、力を解放すればバネのように元の形状に戻る特性を持つ。リボーンチャレンジをもって初披露する金属製ベローズは、宇宙開発・宇宙産業の分野における機能面に対する考え方を一新。コンパクトに畳むことができ、使用時には機器同士を繋ぐために自在に伸縮させて使える特性を持たせた。輸送時の限られた空間を有効活用する省スペース化と、利便性を兼ね備え、将来性がつまった開発品に宇宙への大きな期待を込めた。
展示方法にも趣向を凝らす。展示品のフレキシブルチューブとベローズが、医療現場や宇宙空間で使われている未来を空間型VRで演出。映像と実物の両方から視覚に訴えかける。医療と宇宙の最先端提案を、フィナーレに向けて盛り上がる万博の空間で触れてほしい。
髙丸工業、ロボット業界のマイクロソフトを目指す
万博会場からリモート溶接を実演
髙丸工業は8月21日、大阪・関西万博の会場から兵庫県西宮市の自社工場に設置したロボットを遠隔操作し、来場者によるリモート溶接体験を行った。一般来場者が産業用ロボットを使って実際に溶接を行う試みは初めてだという。
産業用ロボットは通常、操作パネルがメーカーごとに異なり、熟練技術を持つ限られた人しか扱えない。日本では「ロボットを自在に動かせるのは1万人に1人」とも言われる難易度の高い分野だ。こうした壁を越え、「誰でも扱える産業ロボット」を目指したのが、同社が開発した遠隔PC操作溶接ロボットシステム「WELDEMOTO」である。

リモート溶接を体験する万博来場者と使い方を教える髙丸泰幸専務(奥)
開発を主導したのは、現社長・髙丸正氏の夢を受け継いだ髙丸泰幸専務。直感的な操作を可能にしたインターフェースにより、溶接経験のない社員でも短時間で作業をこなせるようになり、海外との遠隔操作も実施した。「業界向け展示会では紹介してきましたが、一般の方に体験いただくのは今回が初めて。子どもから高齢者まで、幅広い方に操作してもらい、生のフィードバックを得られたのは大きな収穫でした」と泰幸専務は語る。会場では「矢印が小さい」「画面が見づらい」といった体験者からの率直な意見も寄せられ、今後の改善に活かす考えだ。
■食品業界にも展開
さらに「WELDEMOTO」を単なるロボットシステムではなくプラットフォーム化する構想も掲げる。実際食品産業など異分野への展開も動き出した。正社長も「溶接が誰でもできることを万博で実証できた。私たちは本気で“ロボット業界のマイクロソフト”を目指しています。専務は『事業を倍に』と言っていますが、プラットフォーム化できれば“一万倍”も夢ではない」と大きな期待を寄せる。
実際に体験した兵庫県在住の50代女性は「熟練の技が必要とされる溶接を簡単にできました。もし実際、家にいながら溶接が可能な世の中になれば、仕事として挑戦してみたいです」と驚きを交えて語った。
エア・ウォーター、万博で「遠隔調理」実証実験
ロボット活用ジェラートを提供
大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン「ミライと食の文化ゾーン」に出展中の「AIR WATER NEO MIX STAND」で、ロボットが作る「ミライのミックスドリンク」を提供している産業ガス大手のエア・ウォーター。8月26日から30日にかけ、デモキッチンエリアにおいて辻料理教育研究所の協力のもと、辻調理師専門学校の学生が遠隔地からロボットを操作し、未来の「遠隔調理」の可能性を探るジェラート作りを実証した。
今回の実証実験「ミライのジェラート作り&サイエンスショー」では、同社の祖業である産業ガス技術が活かされた。液体窒素を用いることで材料を瞬時に冷凍し、きめ細かく滑らかな口どけのジェラートを実現している。レシピは同社グループ内で開発されたもので、ベースには飲料製造販売を手掛けるゴールドパックの製品を使用。さらに、スイーツ製造販売のプレシアが製造したタルト生地の端材をアクセントとして加えることで、グループ各社の技術と製品を融合させた。

液体窒素を注ぎ入れる協働ロボット
イベントを主催したエア・ウォーターのロボティクス自動化プロジェクトリーダー・仲橋孝博氏は、リモート調理システムの中核技術としてデジタルツインの活用を強調した。「リアルタイムで取得したロボットの動作データを仮想環境(バーチャル)に反映させ、シミュレーションを行うことで、実際のロボットを正確に制御しています」と説明する。このシステムは、自動化ラインだけでなく、店舗や工場の空間設計から仮想的に構築できるのが特徴だ。
■デジタルツイン技術を駆使した遠隔制御システム
常設の「AIR WATER NEO MIX STAND」では、多数のセンサーが設置されており、遠隔地からロボットシステムの稼働状況を監視している。これにより、現場スタッフが問題に直面した場合でも、遠隔地から状況を正確に把握し、適切な指示を出すことができる。特に、食品分野における自動化普及のためには、操作のハードルを下げることが重要だ。このシステムは、専門的な知識や経験のない人でもロボットと協働できるようなインターフェンス設計がなされており、POSレジとの連携も行っている。
仲橋氏は「万博での実証実験を通じて得られたシステムとノウハウを、まずグループ内の食品関連企業だけでなく様々なジャンルの企業で試し、その後は外販も視野に入れたい」と語り、デジタルツイン技術のシステムやソフトウェア販売によるマネタイズ(収益化)に意欲を見せた。
TAMAYURA、万博でコシノジュンコ トークショー
「仕事着」の魅力語る

手掛けたワークウェア「Mr.JUNKO WORK WEAR」をバックに『胸ポケットの差し色でチャーミングに』とこだわりを語ったコシノジュンコ氏
1970年の大阪万博でコンパニオンの衣装を手がけた世界的デザイナーのコシノジュンコ氏。55年の時を超え今回の大阪・関西万博でシニアアドバイザーとしてボランティアユニフォームなどのデザインを監修した。二つの万博で「働く人」のシンボルともなる衣装に携わったコシノ氏は、9月4日に大阪・関西万博会場にてTAMAYURAが主催したトークショー「万博のデザイン」で思いを語った。
江崎グリコやタカラベルモントなどの企業のコスチュームを手がけ、ボランティアのユニフォームを監修したコシノジュンコ氏は今年の大阪・関西万博でも存在感を発揮する。医療スタッフや清掃スタッフまで多くの人が作業をしながら着用するユニフォームは、ポケットを多くし、機能性を持たせた。鮮やかなツートーンの配色などデザイン性にもこだわり、万博の景色に彩りを添える。
70年の大阪万博では、ペプシ館やタカラベルモントなど3つの企業パビリオンの衣装を20代での若さで大役を引き受けた。地下足袋風のストレッチブーツやミニスカートのシルエットなど斬新なデザインで話題を呼んだ。
■ワークウェアのデザイン手掛ける
TAMAYURAを通じ、南海電鉄やリーガロイヤル大阪の新たなスタッフユニフォームを一新したコシノ氏。TAMAYURAとコラボして生まれたワークウェア「Mr.JUNKO WORK WEAR」では従来の作業着と一線を画し「着たい」ワークウェアを実現した。手を入れて出し入れやすい縦ファスナー付きポケットなど機能性を第一に、動きやすさと安全にもこだわる。
「TAMAYURAの岡本哲社長との出会いで初のワークウェアのデザインに挑んだ。人の出会いで仕事が広がっていく」と語り、「赤と黒、白と黒などスタイリッシュかつチャーミングにまとめた。着やすさがありながら『いい仕事をしたくなるウェアを』と応援団のつもりでデザインした」と魅力を説明した。
大阪・関西万博発
「OSAKA JAPAN SDGs Forum」開催
大阪府は、「Osaka SDGs ビジョン」(令和2年策定)で目標に掲げる、大阪・関西万博の開催都市として、世界の先頭に立ってSDGsの達成に貢献する「SDGS 先進都市」の実現に向け、オール大阪でSDGsの新たな取組みの創出を図っている。その一環として、大阪・関西万博会場内のEXPOホール「シャインハット」にて、「OSAKA JAPAN SDGs Forum」を9月5日に開催。第一部では基調講演や産官民によるパネルディスカッション、第二部では演歌歌手・中村美律子氏による歌唱パフォーマンスや学生らによる発表、講演とパネルディスカッションが行われた。
主催者挨拶では、大阪府の吉村洋文知事が「大阪府は、世界の先頭に立ってSDGsの達成に貢献する『SDGs先進都市』の実現をめざしています。万博イヤーである今年は、これまでの取組みをパワーアップし、本フォーラムを開催しています。『みんなの知恵をつなげて、世界を変えよう』をコンセプトに、皆様と一緒に培ってきたことや、皆様が普段から行っていることを積み上げて、SDGSのアクションを次に繋げていけたらと思います」と話した。
基調講演では、国連事務総長の任命を受けた独立科学者15人の1人として、グローバル持続可能な開発報告書(GSDR 2023)の執筆を行なった蟹江憲史教授が「2030年まであと5年ですが、SDGSはそこで終わりではなく、その先も続いていく必要があります。地域や企業などの小さな単位で、その文化・伝統に基づいて未来を見据えた行動を行い、一つ一つの努力を繋げて行動の輪を広げていくことが最も大切です」と述べ、日本におけるSDGSへの高い認知度や地方自治体の活動が「変革」を加速する可能性について語った。そして、経済に頼らない成長や将来世代との協働、さらに、地域の活動を繋げることが、2030年以降を見据えたBeyond SDGSに向けて不可欠であると強調した。
山善TFS/大阪・関西万博に出展
協働ロボットが人と共存する社会を提示
機械工具商社「山善」のトータル・ファクトリー・ソリューション(TFS)支社は、9月1日から15日までの15日間、大阪・関西万博の未来社会ショーケース事業「スマートモビリティ万博」内の「ロボットエクスペリエンス」にて、『ロボットが撮るんです。』展を実施した。1970年の大阪万博には出展しておらず、今回が山善にとって初めての万博出展となる。産業分野における工場での自動化に不可欠な協働ロボットを、今回の出展を通じて一般の人々に身近に感じてもらう狙いがあった。

ブースの様子
入口に設置されたモニターでは、歴史を紐解きながら、現在から未来へとつながる人間とロボットの共存社会のイメージが映し出された。現在、労働人口の減少に伴う人手不足が深刻化する中、人間と同じ空間で安全に作業できる協働ロボットの需要は高まる一方である。デロイトトーマツコンサルティングの調査「ロボット未来予測2033」によると、2033年には世界市場が3兆円規模になると予測されている。
今回の展示では、一般的に「工場や生産現場で動く機械」というイメージが強い協働ロボットの概念を覆し、「自動撮影システム」を通じて、ロボットが身近な存在・生活に欠かせない存在に感じられるようにエンターテインメント性をもったシステムを紹介した。
展示では、雷門、東京タワー、大阪城、ラベンダー畑といった日本の名所の背景データが入力された白いカードが10枚用意された。体験者がランダムに選んだ背景に合わせて、ロボットのアームが最適な位置に動き、カメラアングルなどを自動で調整。「映える」写真を撮影し、プリントした写真が来場者に無料でプレゼントされた。また、日本の伝統芸能である「獅子舞」の装飾を施した協働ロボットも来場者の注目を集めた。来場者は、協働ロボットとの体験を通じて、「ロボットと共存する社会」のイメージを楽しみながら実感できる内容となった。
■テックマンが魅せるエンタメ
今回使用された協働ロボットは「テックマン」である。世界最大級のノートパソコンメーカーであるQuanta Computer社を親会社に持つ、台湾唯一の協働ロボットメーカー、テックマンロボット社が製造している。カメラが標準搭載されており、簡単なプログラミングが可能であることが特長だ。また、AIが搭載されたシリーズは、画像を用いたディープラーニングが可能で、組み立てや搬送だけでなく、部品の種類ごとの選別や傷・汚れなどの不良品検出にも活用される。
山善は、テックマンロボット社の正規代理店として、日本の製造業を中心に導入をサポートし、年間トップクラスの台数を製造業界に納入している。また、大阪市淀川区(新大阪駅徒歩圏内)にある協働ロボットトライアル施設「協働ロボットテストラボ」のトレーニングルームでは、テックマンロボット導入時の操作トレーニングに加え、導入企業向けの「産業用ロボット安全特別教育」も実施している。山善トータル・ファクトリー・ソリューション支社 技術サポート部 ロボティクス室長の谷口文晶氏は「日本は国土が狭く、小さな工場が多いため、産業用ロボットが導入できない場所も少なくありません。中小企業の皆様に貢献するためにも、協働ロボットの普及を目指しています」と語る。

山善TFSの谷口文晶氏
■ヘルメットなしの一般来場者環境での安全稼働
工場などで稼働する協働ロボットを、ヘルメットや安全靴を着用していない一般来場者が多数集まる、また間近まで接近する環境で安全に稼働させるには多くの苦労があった。谷口室長は「エリアセンサーがあってもロボットを早く動かすわけにはいきませんでした。また、エンターテインメントとして協働ロボットを動かすという我々にとって未知の領域で、想定以上の制約の中、ダイナミックに動かすのに苦労しました」と話す。
万博協会との綿密なリスクアセスメントが幾度も行われた。撮影用カメラや獅子頭が落下しないよう様々なトルク値を試した結果、最終的にはインシュロックで落下を防ぐというアナログな安全対策も実施し、『ロボットが撮るんです。』を完成させた。プリクラの中身が動き出すような、展示に仕上げるには様々な苦労があった。

ロボットが撮るんです。での撮影風景
また、「獅子舞」の展示は、少子高齢化によって継承が難しくなっている日本の伝統芸能を協働ロボットで再現する試みでもある。谷口室長は、「獅子舞に限らず、陶芸や漆塗りなど、後継者不足に悩む伝統文化に協働ロボットをいかに活用していくか、考える機会になります」と述べた。
今回の展示を通じて、協働ロボットは世界各国からの来場者に「未来に残したい思い出作り」を提供した山善。
多くの人が訪れたこと、また、この展示を通じてロボットエンジニアやロボットSIerを目指す子どもたちが増えてほしいという山善TFS支社の願いもあり、「当社の新大阪にある『協働ロボットテストラボ』で、子ども向けのロボット教室も検討していけるかもしれません」と、谷口室長は笑顔で語った。
ドコモ初、回収品をリサイクル利活用した「エコハードケース」
NTTドコモは、ユーザーからの回収品をリサイクルして自社商品へ利活用したスマートフォン用ケース「エコハードケース」(写真)を開発。9月19日からドコモショップ、ドコモオンラインショップで発売する。
また、経済産業省が9月23日~29日に大阪・関西万博で開催する「サーキュラーエコノミー研究所」に出展し、同商品を展示する。

SIMカード枠をリサイクル、利活用してエコハードケースを開発
同社は、資源循環型社会の実現を目的に1998年から携帯電話のリサイクル活動「ドコモ ケータイリサイクル」に取り組む。ユーザーのSIMカード枠はリサイクルして資源として売却していたが、この度新たに自社のサプライチェーンで利活用した商品を開発した。
ドコモグループでは、社会全体の持続的な発展と地球環境に貢献するためのアクションを「Green Action Plan」として定め、2030年には廃棄物リサイクル率99%を目標に、3R活動の推進や携帯端末回収の促進などに取り組む。また、「生物多様性中期ロードマップ」の中でも資源循環を促進し、マテリアルリサイクルを推進していくことを掲げる。
同社は「今後も提供する商品・サービスの調達から廃棄に至るまでのライフサイクル全体を通じて資源を有効利用し、サーキュラーエコノミーの取り組みを推進することで、社会全体の持続的な発展と地球環境保全に貢献してまいります」とした。
(日本物流新聞2025年9月25日号掲載)