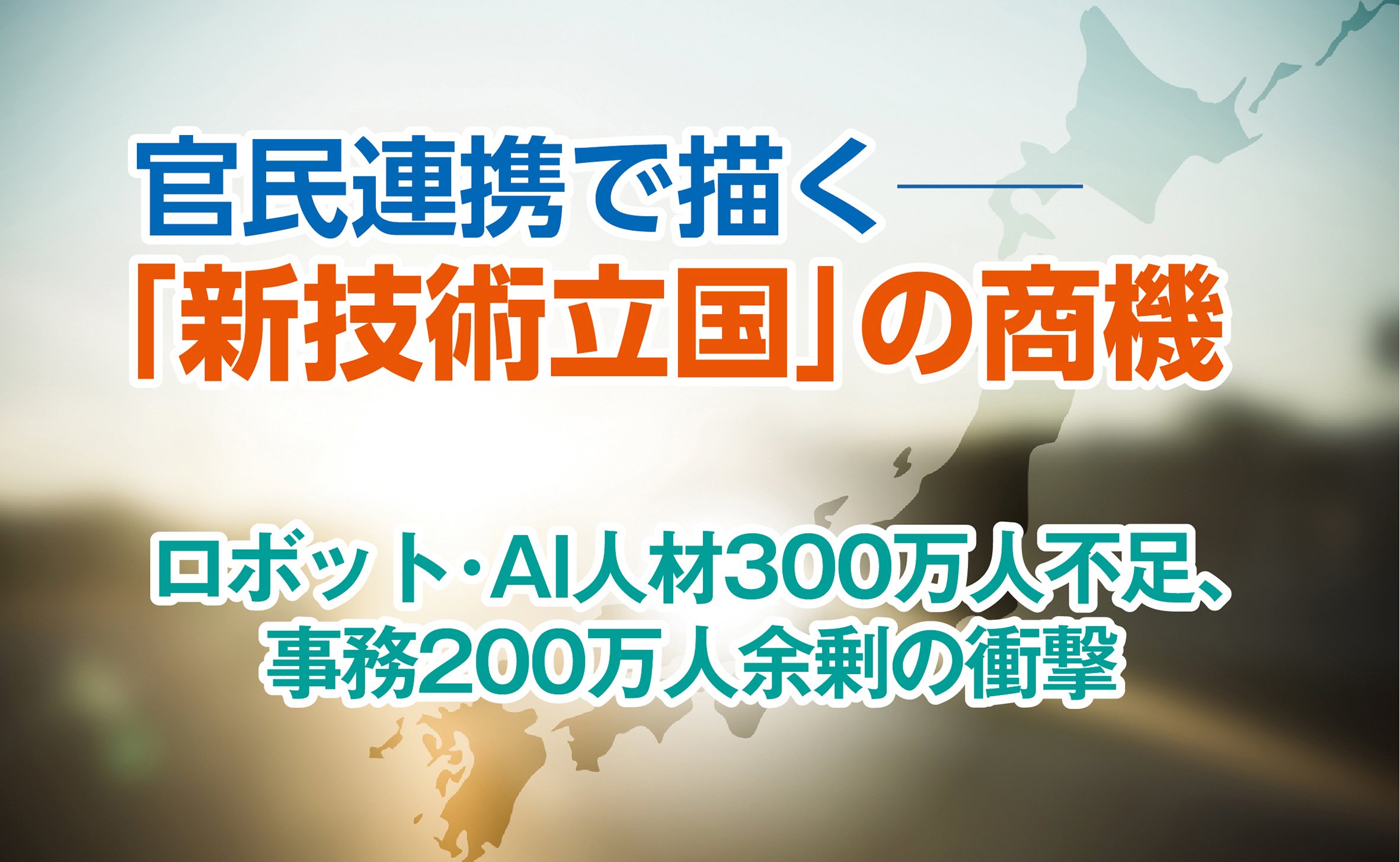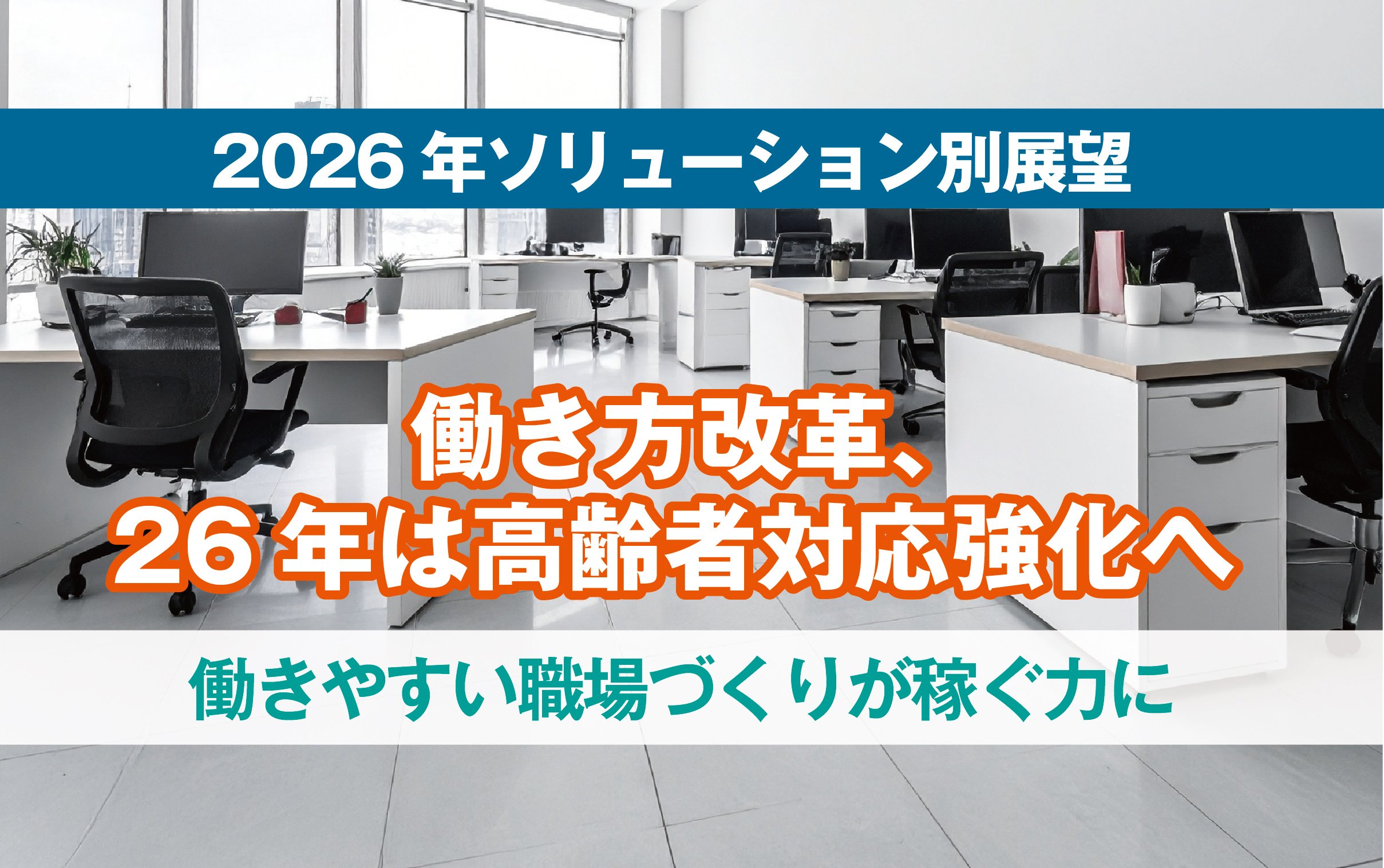山善「ロボこたつ」徹底解剖
- 投稿日時
- 2025/01/07 13:56
- 更新日時
- 2025/01/07 14:10

ROBO−COTATZ(Corporated Technical Aid of Toho And YAMAZEN)
山善のTFS(トータル・ファクトリー・ソリューション)支社と山善グループでロボットSIerの東邦工業が、多品種少量生産の現場を自動化するモビリティシステム「ROBO-COTATZ(ロボこたつ)」を共同で開発、11月28日に発売した。こたつの形をした台座をAMRが運び、複数の工程で協働ロボットを共有することで現場をミニマムな投資で自動化する。必要な設備を必要な時に必要な場所へ――これを叶える同システムの性能を、開発背景や山善TFS支社・東邦工業両トップへのインタビューも交えて徹底解剖する。
ロボットも、AMRも使い倒す
ロボこたつは複数の工程でロボットを柔軟に共有できるシステムだ。作業の要領としてはまず、協働ロボットが載ったこたつ型の台座をAMRが下に潜りこんで持ち上げ、作業を行うエリアへと運ぶ。搬送が終われば台座とAMRは速やかに分離してAMRは別の方向へ走り去っていく。これによりロボットが作業を行う間もAMRは休まず他のタスクをこなすことができる。
つまりロボこたつは、ロボットとAMRの台数をともに最小に抑えられるコストパフォーマンスの高い自動化システムと言える。導入にあたり大幅なレイアウト変更も不要で現場の負担が少ない。なおこたつ本体にロボットコントローラーや通信機器を搭載し、非接触給電が可能なバッテリーも積んでいるため電源確保の懸念もない。
人手不足でいまやポピュラーになった協働ロボットやAMRだが、実は日本に多い多品種少量生産の現場はいまだ導入に踏み切れていないケースが多い。理由は多品種生産ではロボットやAMRの台数ばかりがかさみ、それぞれが限られた時間しか稼働せず費用対効果が低いからだ。AMRと協働ロボットを一体化させればロボットの稼働率は上がるが、今度は協働ロボットの稼働中にAMRが動けなくなるうえ故障時は共倒れするなどリスクも高まってしまう。ロボットや電源など必要な機能をこたつ型ユニットにまとめてAMRと分離可能な構造にすることで、どちらの機器も最大限、「使い倒す」ことができるようになる。
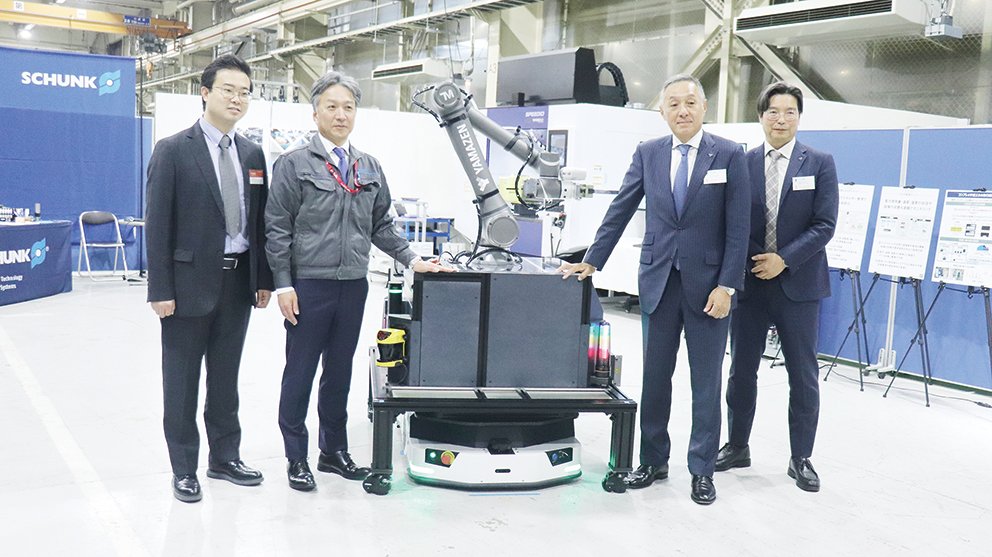
左からYOUIBOT Zhang Chaohui CEO、東邦工業 丸山洋彦社長、山善 中山勝人TFS支社長、山善 TFS支社 植島代志和技術サポート部長
何をするか・何を運ぶかは現場の数だけ答えがある
ロボこたつはテックマン社の協働ロボットとYOUIBOT社のAMRを組み合わせるのが標準形だ。AGVの繰り返し停止精度にはどうしても±5~10㍉の誤差があるが、テックマン社の協働ロボットは標準でカメラを装備しており、移動先でランドマークを読み取ることで位置の補正ができる。カメラで部品の種類ごとの選別や傷・汚れなどの不良品検出も可能。またYOUIBOT社は中国の半導体製造工程で使われるAMRでトップの実績を持ち、複数台のAMRを効率よく運用する「フリート制御」に強い。ロボこたつの柔軟性は両社の強みを持ち寄ることで形作られている。
ただしここに述べた組み合わせはあくまで標準形で、要望に応じてロボットやAMRの機種や組み合わせは柔軟に変えることができる。本体サイズの変更もカスタマイズの範疇だ。
11月28・29日に東邦工業で行われた内覧会では、実際に複数台のAMRを制御しロボこたつで工作機械の段取り替えを自動で行って見せた。ただこれはあくまでロボこたつにできる作業の一例に過ぎず、山善TFS支社長の中山勝人氏は「現場に合った最適なソリューションを提供できる」とする(上にインタビュー記事)。
4台のロボットが1台にスリム化
例えばネジ締めや検査を協働ロボットが行うのも活用方法の一例だ。そもそも台座に協働ロボットを搭載せず、ストッカーや駆動コンベヤ、検査装置などそれ以外の機器を搭載することもできる。あくまでロボこたつは自動化のためのベースで、その先で何をしたいかはユーザーが希望を出し、TFS支社と東邦工業がそれをシステムとして具現化する形。つまりロボこたつはあくまでハードで、その先で何をするかのソフト部分が同システムの核だ。
例えば組立と検査のラインが2つずつ、計4ラインある工場の場合。各ライン2時間の作業ボリュームだとすれば、通常なら協働ロボット4台とAMRが1台必要だが、ロボこたつなら協働ロボットもAMRも1台で済む。「複数個所でロボットを使う」、あるいは「ロボットの使用時間が限定的」「段取り替えが多い」「AMRを単体で使いたい」。いずれかに心当たりがある現場はロボこたつでコストを抑えた自動化が叶うかもしれない。
ロボこたつは東邦工業とTFS支社が共同で開発したシステムだ。東邦工業は2017年に山善グループに参画した創業74年目の企業で、オーダーメイドの製造装置の設計開発を得意とし、ロボットSIerとしても活動する。なお両社が協業して標準化した製品を世に出すのは初の試みだという。
中山支社長は「TFS支社として、今期の自動化案件の受注目標である100億円を目指し営業活動に注力する」と語る。その上でロボこたつは大きな武器となる。
山善 中山 勝人 TFS支社長
ロボこたつは「やりたい」を具現化するツール
稼働率に悩む現場の現実的な「解」に

――ロボこたつの開発経緯は。
「実は私が昨期の初め、技術サポートチームに『AMRと協働ロボットを使い商品開発ができないか』と要望を出したんです。AGVが爆発的に増えていますが、いずれはAMRがより大きな市場を取るだろうという予測が頭にありました。しかもAMRとロボットが分離できれば一体型と比べAMRの台数も減らせるという発想です。我々も製造現場でAMRと協働ロボットの需要は数多く頂いていましたが、AGVの繰り返し停止精度は下手をすれば㌢単位で変わるので高精度が求められる協働ロボットの作業と相性がよくない。ところが我々が代理店を務めるテックマン社の協働ロボットはカメラを標準装備しており、位置補正ができるんです」
――ロボこたつは標準化された製品でありつつ、ロボットが何をするかは現場ごとのカスタマイズ、つまりTFS支社の腕の見せ所ですね。
「ロボこたつで提供するのはあくまで自動化のヒントであり、後はお客様の側でどういう使い方を想像して頂けるか。どの工程・現場で使えるかは我々が勝手に限界を決めるべきでなく、極端な話まったくの自由です。今日の内覧会(※2024年11月28日に取材)は工作機械との連動で金属部品の搬送をお見せしましたが、例えばネジ締めや測定ユニットを載せても良い。エレベーターと連携させたデモも、本来はロボット連携が想定されていない設備と無線で連携できることを示すためです。内覧会には生産技術など製造のプロの方々が来場されますが、ぜひ自由に使い道を想像して頂きたい。後は我々がそれを形にします」
――AMRとロボットを100%使い倒すという発想の商品です。実際、それらを導入したのに稼働率が低い現場は多いのですか。
「今は経営者層から現場へAMRの導入を進めるよう指示が出ています。ただ実際に導入したもののうまくいかない、つまりは使い切れない現場は数多く目にしてきました。また私自身の過去の納入経験を踏まえても、AGV・AMRは位置補正が必要で上にロボットを載せると特にメカチャックでワークを掴む作業が難しい。スピードを重視するあまり十分な検証を経ずに導入した現場の多くが苦労されています。背景には、そもそもロボットとAGV・AMRをシステムインテグレートできるSIerが少ない、という事情もあります。山善グループにはロボットの扱いに長けた東邦工業が、TFS支社にはAGVに熟達した人材が複数おり、協力体制で稼働率を上げられる商品を開発できました。グループに必要なピースが揃っていたんです」
――ロボこたつへの期待感は。
「本当に色々な業種の方々から具体的なお話を頂いています。お客様もわかりやすく我々も提案しやすい商品。期待は大きいです。一方、TFS支社のコンセプトであるお客様のお困りごとをトータルで解決するという方針は不変で、一品一様の自動化システムも従来通り、いや今まで以上に提供していきます。TFS支社の自動化案件の受注も目下右肩上がりです」
――ところでロボこたつの実機はどこで見られますか。
「実機は設備や検証の環境が整った東邦工業に常設予定です。東邦工業は近年、VRを使ったシミュレーションに力を入れておりロボこたつもVRで検証できるようになるかもしれません。ご興味がありましたら、ぜひ広島へお越しください」
東邦工業 丸山 洋彦 社長
ロボこたつの開発経験が新たな武器に

おかげさまで内覧会は盛況で、想定より多くの方にロボこたつ、ひいては東邦工業のソリューションに興味をお持ち頂き嬉しく思います。
ロボこたつは良い物ができたと思います。ロボットもAMRも決して安い設備ではないからこそ、それぞれの稼働率を高めたいのはユーザー側の普遍的な心理です。AMRと台座ユニットが分離して動く構造にするためにはロボットコントローラーやバッテリー、コンプレッサーなど様々な機器を小型の筐体に収める必要があり、まさにこの部分に東邦工業の設計力が活きました。詳しくはノウハウなので明かせませんが、各機器との連携はすべて無線による通信で行い、給電も非接触です。総じて容易に後追いできない完成度の高いシステムに仕上がったと自負しています。
我々は元々AMRの知見はなかったのですが、YOUIBOT社の実機を半年間いじくり倒した結果、非常に豊富な知見を得られて視野が広がりました。YOUIBOT社と信頼関係も醸成され『もっと色々やりましょう』と評価頂いています。
ロボこたつの開発では東邦工業が設計や製造、検証を担いました。一方、テックマンロボットやAMRではTFS支社の技術サポートチームと相当、密なやり取りを行い力を借りました。まさに両輪で形にした商品です。
東邦工業は製造装置のオーダーメイド製作が得意で2018年にはロボットSIer協会にも加盟しています。近年は非常に多くの仕事を頂き、大変忙しい状況が続いています。新規のみならず改造案件も多く、これは今までお客様の信頼を得て納入した設備が非常に多いことの裏返しです。
今まで目の前の仕事に全力で取り組んできましたが、ロボこたつの開発と前後して経験豊富な人材を採用し「特命チーム」を作りました。本業と切り離し自由な立場で開発を行うポジションです。これがロボこたつの開発でも功を奏しました。今後もこの機能を強化します。さらに人材を厚くしAMR専門部署の立ち上げも計画しています。
ロボこたつは山善が販売しますが我々はそのぶん、技術面をブラッシュアップし改良やコスト改善に努めます。「応用編」になりますがネジ締めや溶接など建設現場での活用も将来的には期待できるのではないでしょうか。それにはアプリケーション開発が重要で、ソフトメーカーなど他社とどれだけ協業できるかが勝負です。山善のネットワークも活用して輪を広げ、もっと面白い展開を加速します。
MEMO 東邦工業
1950年創業。自動車の製造ラインに使うオーダーメイド装置の設計製作が得意で、2017年に山善グループに参画。18年にロボットSIer協会に加盟した。近年はシミュレーションに力を入れ、装置の製作前に仮想で動作検証を行い実物を重ねるデジタルツインを推進する。強みはエンジニアリング力だが丸山社長は「それが課題だ」と指摘。人材採用や育成を強化し、その一環で工場やオフィス環境に大規模な投資を行った。現在はSIer企業等の外部ネットワークを拡大中で、阿吽の呼吸のパートナー企業を増やしキャパシティの強化を目指している。
(日本物流新聞2024年12月25日号掲載)