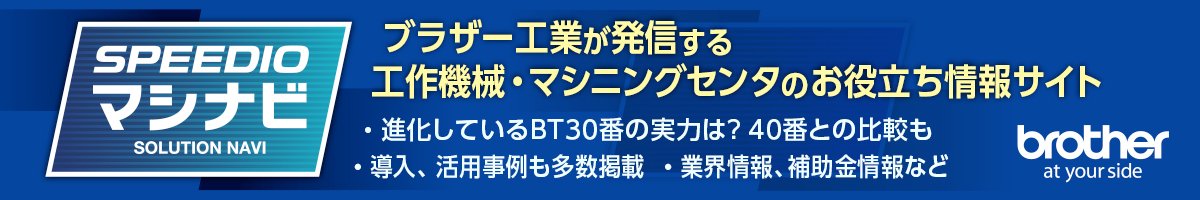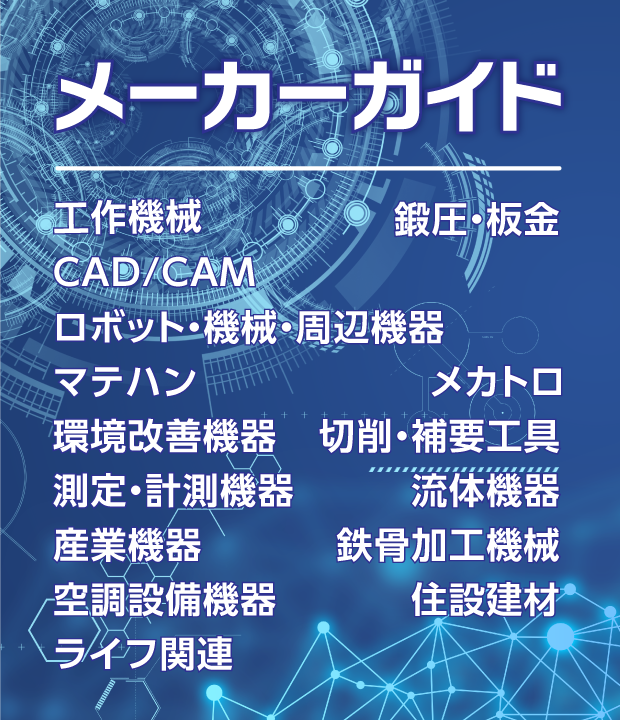【2026年新春産業展望】自動車産業の先行きは 記者による振り返りと予測
- 投稿日時
- 2026/01/08 14:56
- 更新日時
- 2026/01/08 16:18

日本の自動車大手7社の2025年度4~9月期中間決算では、トランプ関税の負担額が合計1兆4000億円に達した。トヨタ自動車は通年で関税コストを1800億円と試算し、営業利益が前年度比約1000億円減少する見通しを発表。ホンダは関税コストを4500億円と見込み、営業利益が前年度から7134億円減少して5000億円になると予測した。日産、マツダ、三菱は赤字に転落し、日本の自動車産業は深刻な打撃を受けることとなった。
韓国の現代自動車グループも、2025年7~9月期の関税措置による損失が約3300億円に達し、前四半期から89%増加したと発表。米国生産比率の低い韓国やドイツのメーカーへの影響は特に大きく、各国企業は米国内での生産拡大を迫られることとなった。

関税問題により大幅な損失を計上した現代自動車
もう一つの大きな変化は、欧州連合(EU)が2025年12月16日に発表した、2035年以降の内燃機関車販売禁止方針の事実上の撤回である。EUはこれまで2035年に新車のCO2排出量を実質ゼロとすることで、エンジン車の販売を原則禁じる方針を掲げていたが、新提案では目標を「2021年比90%削減」へと緩和し、一定の条件を満たせばプラグインハイブリッド車やエンジン車の販売も継続できることとした。
この方針転換の背景には、EV販売の大失速がある。欧州では2023年後半から補助金の終了・縮小に伴い、EV販売が減速。多くのメーカーが生産調整や人員削減を余儀なくされた。欧州自動車部品工業会は、今後5年間で自動車部品関連業は約5万4000人の人員削減が見込まれていると予測するなど、業界全体が苦境に立たされている。
メルセデス・ベンツは2025年2月、「2030年までに完全なEVメーカーになる」という目標を取り下げ、次世代内燃エンジン開発に約2兆200億円を投じると発表。ボルボも同年9月、「2030年までにBEVメーカーになる」としていた方針を後退させ、「2030年までにEVとPHEVの合計で販売比率の90%以上を目指す」と修正した。これまでのEV一辺倒から全方位戦略への転換が、欧州自動車業界の新たな潮流となっている。
こうした中、存在感を増したのが中国自動車メーカーだ。BYDは2024年に前年比40%増となる427万台を販売し、世界ランキング7位に浮上。300万台規模の日産やホンダを超え、6位のフォードともわずか20万台差に迫る勢いを見せた。BYDの成功要因は、バッテリーの内製化による圧倒的な価格競争力と、EV需要の弱含みを見据えてハイブリッド車を低価格で素早く市場投入した商品戦略にある。

ハイブリッド車も好調なBYD
勢いを増す中国勢に対し、EUは中国製EVに対する相殺関税を課すことを決定した。だが、BYDはハンガリーやスペインでの生産を開始。奇瑞汽車はスペインで合弁工場を稼働させ、小鵬汽車はオーストリアのマグナに生産委託するなど、一部の中国メーカーはEU域内への生産移管を図るなどの対抗策を講じている。
■試練の日本自動車産業
日本国内の自動車市場は、2025年度上半期(4~9月)において2年ぶりに前年同期比0.5%増となり、わずかながら回復の兆しを見せた。しかし、その内実を見れば、勝ち組と負け組が明確に分かれる構図が浮かび上がる。
最も深刻な状況に陥ったのは日産自動車である。2025年度上半期の国内販売台数は前年同期比16.5%減の18万5672台となり、1993年以来で最低の水準を記録した。軽EV「Sakura」の販売こそ堅調だったが、それ以外の車種が壊滅的で、営業マンが口々に「売るクルマがない」と嘆息する1年だった。

日産の新エルグランド
加えて経営問題によるブランド力の低下も響き、コロナ禍前と比較すると33.9%も減少している。経営不振から2024年末にホンダ、三菱自動車との3社協業形態について検討を開始したが、2025年2月には白紙となり、独自での再建を目指すこととなった。
同3月には新たにイヴァン・エスピノーサ氏をCEOに据えた経営体制を発表。ポジションを約2割削減する大規模なリストラに加え、主力生産拠点の追浜工場の閉鎖を発表するなど、大胆なコストカットを行う見通しだ。
今後は新型エルグランド、新型リーフや大型SUV「パトロール」の日本市場投入などで巻き返しを図る。
一方、トヨタ自動車は相対的に安定した業績を維持している。トランプ関税の影響により通年の営業利益は前年度比で約1000億円減少する見通しだが、佐藤恒治社長は「足元の収益・事業構造上、ジタバタしなくてはならない状態にはない」と余裕を見せる。
トヨタの強さの源泉は、ハイブリッド車にある。世界的にEV一辺倒の戦略が見直される中、トヨタが長年培ってきたハイブリッド技術の価値が再評価されている。トヨタグループの部品メーカー各社も、ハイブリッド車向けの利益率の高い部品や先進運転支援システムの売上高が順調に拡大。さらにBEVの失速により、オートマチック製品などで残存者メリットも発生している。

ホンダは2025年、トランプ関税により営業利益が前年度から7134億円減少、5000億円になるという厳しい見通しを発表した。関税への対応策として、「シビック」の5ドアハイブリッド車と「CR-V」について、日本とカナダから米国へ生産移管を計画している。
国内販売も前年同期比11.6%減と苦戦が続いた。軽自動車「N-BOX」は依然として国内販売のトップを堅持しているが、それ以外の車種の販売が伸び悩んだ。EV分野でも米国でのEV補助金打ち切りを受け、生産計画を見直したため2237億円の一時費用が発生するなど、電動化戦略の修正を余儀なくされている。
日本政府は2035年までに新車販売を電動車100%にする目標を掲げているが、2025年11月時点での日本国内のEVシェアは2.8%に留まっている。前年同月の2.9%から若干減少しており、日本のEV普及は遅々として進んでいない。
興味深いのは、2025年の燃料別シェアではハイブリッド車が49.8%を占め、電動車全体では52.7%に達していることだ。これは、日本が欧米とは異なる独自の電動化路線を歩んでいることを示している。欧州が「ゼロエミッション車9割+エンジン車1割」という厳しい規制を維持する一方、日本はハイブリッド車も含めた「マルチパスウェイ」アプローチを取っている。
この戦略はEUや米国の動きを見ると、結果的に現実的な選択であったことが証明された形となった。日本の自動車メーカーが長年培ってきたハイブリッド技術は、グローバル市場における競争力の源泉として、改めてその価値を高めている。
2026年自動車産業展望
不透明な先行きに曇天模様続く
世界の自動車産業は2026年、電動化一辺倒の時代から、より現実的な競争局面へと移行する。EV(電気自動車)の成長は続くものの、各国で需要の伸びは鈍化し、メーカー各社は収益性と技術投資のバランスを問われる年となる。
「100年に一度の変革期」と言われて久しい自動車産業。だが、国内・国外共に本格的な設備投資で業界全体が右肩上がりに、とはなっていない。自動車産業の成長の足かせとなっているのは、明らかにEVだ。
中国のような特殊なマーケットを除き、基本的に消費者はEVを求めていない。購入するのは環境意識高い系の消費者や、サステビリティアピールをしたい経営陣くらいで、そもそも利便性に劣るクルマを、一般ユーザーに内燃機関車より高い値段で買うという選択肢が無い。それゆえ、コロナ禍以降「設備投資の様子見」がしばらく続いているのが現状だ。
各シンクタンクや本紙を含む報道は、ここ数年希望的観測も含めて「来年は設備投資動向に進捗が」「ハイブリッド車需要で日本自動車産業が復活」など、明るく甘い見通しを繰り返してきた。だが、現実的には今年を含め2030年くらいまでは「曇り」の状態がしばらく続くと思われる。
2026年、世界の自動車産業における最大の焦点は中国市場だ。中国は依然として世界最大の自動車市場であり、EV普及率も高いが、2025年以降、価格競争の激化が深刻化している。BYDをはじめとする中国勢は、電池から車両までを垂直統合する強みを生かし、低価格モデルを次々に投入。加えてハイブリッド車市場にも参戦し、世界シェア拡大に挑む。対する欧米・日系メーカーはシェア防衛に一層苦しむことになるだろう。
欧州では環境規制の厳格化が続く一方、消費者のEV購入意欲は踊り場を迎えた。高価格、充電インフラ不足、残価不安といった課題が顕在化し、各メーカーはPHEV(プラグインハイブリッド)や単価の安い小型EVへのシフトを余儀なくさせられる。すでに欧州自動車メーカーの多くは「全EV化」から「現実解としてのEV&内燃機関車ミックス」へと舵を切っている。
米国市場では、トランプ政権復活を想定した通商政策の不透明感が影を落とす。EV補助金政策の見直しや関税強化が再燃すれば、サプライチェーン再構築は一段と進む。GM、フォードはEV投資のペースを調整し、利益率の高いSUV・ピックアップと電動化の両立を図る戦略を強める。
一方、ソフトウエア・自動運転分野では競争が新たな段階に入る。完全自動運転の商用化は限定的にとどまるが、レベル2+、レベル3の高度運転支援は差別化の要となる。テスラ、中国新興勢、IT企業が主導権を争い、車は「移動するデバイス」としての価値が一層問われる。
世界全体として2026年は、台数拡大よりも「どこで、どう稼ぐか」が明確に分かれる年となる。過剰投資の調整、提携・統合の動きが加速し、勝者と敗者の色分けが一段と鮮明になる見通しだ。
■日本自動車産業展望
日本の自動車産業は2026年、世界市場の変化にどう適応するかが最大のテーマとなる。EVで先行する中国勢、ソフトウエアで存在感を増す米国勢に対し、日本勢は「多様化戦略」と「現場力」を武器に独自路線を模索する。
最大手トヨタは、EV、ハイブリッド、PHEV、FCV(燃料電池車)を組み合わせる全方位戦略を継続する。2026年にかけてEV専用モデルは拡充されるものの、主力は依然ハイブリッドだ。環境対応と収益性を両立する姿勢は、EV減速局面において大きな強みとなるだろう。
ホンダはソフトウエア定義車両(SDV)に経営資源を集中。EVへの投資額は当初の10兆円から7兆円に減らし、ハイブリッド車のラインナップ強化を図る。また関税問題への対応や米国・カナダでの供給網の再構築により、利益確保が課題となりそうだ。
日産は経営再建計画「Re:NISSAN」を基に、2026年度までに自動車事業の営業利益とフリーキャッシュフローの黒字化を目指す。そのロードマップには生産工場の集約といった、日本自動車産業にとっては確実にマイナスとなる方策が数多く描かれている。

閉鎖が決まった日産・追浜工場
神奈川県下の機械ディーラーは、「追浜ショックにより、当社も売上が激減している。某ティア2のお客さんは『消耗品を買うにも稟議書が必要になった』と購入を渋る」と苦境を嘆く。
日産関連のサプライヤー、特に中堅・中小企業には事業転換のスピードが問われることになりそうだ。
◇−−◇
国内市場全体を見渡すと、人口減少が続くものの、軽自動車や高齢者向け安全技術の需要は底堅い。自動運転レベル2+の普及や、物流・モビリティ分野との連携も進む。今後、自動車メーカーは「車を売る」産業から、「移動価値を提供する」産業へと変貌を迫られる。
それゆえ、日本の強みである「すり合わせ技術」や品質管理は、SDV時代において再定義が迫られる。車両開発の主導権がソフト側に移る中、ハードとソフトを統合する力をどう磨くかが競争力を左右する。
2026年の日本自動車産業は、派手な成長よりも持続性を模索する年になりそうだ。