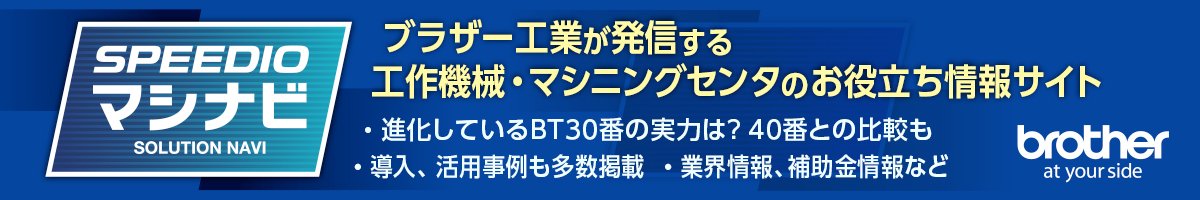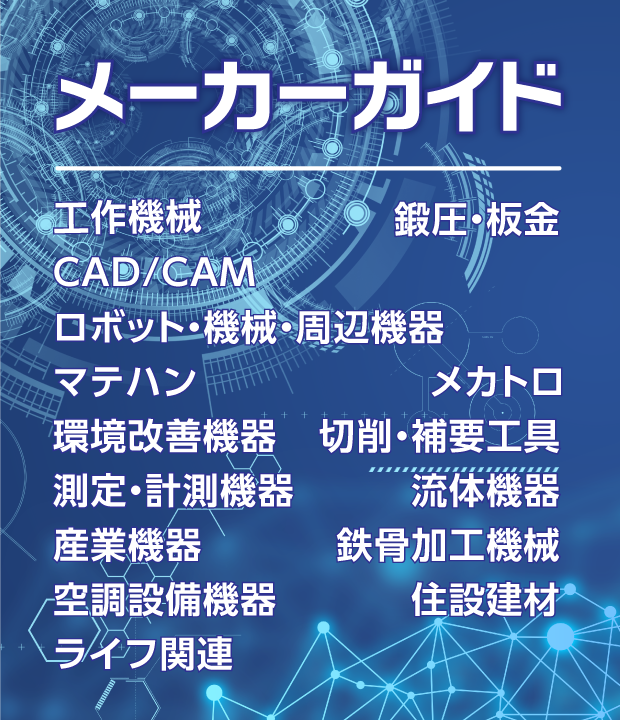インタビュー
オリオン機械 片桐 智美 社長
- 投稿日時
- 2025/12/09 14:27
- 更新日時
- 2025/12/09 14:29
脱炭素への取り組み
創業以来培った冷凍・真空技術を活用し、エアードライヤーや真空ポンプ、チラー、精密空調機などで国内トップクラスのシェアを誇るオリオン機械。優れた省エネ技術をベースとした製品開発に加え、製造現場における脱炭素化にも積極的な取り組みを行っている。そんな同社を牽引する片桐智美社長に現状と今後の展望を聞いた。

――率直に「脱炭素」を理由に製品を導入する企業は増えていますか。
正直に言うと、「脱炭素だから買う」というより、省エネ性を評価して導入される方が圧倒的に多いですね。ドライヤーやチラー単体でCO2を大きく減らせるわけではありませんから。ただ、インバーターモデルや単一ポンプ化など、省エネにつながる仕様は確実に求められています。
――水素発生装置の開発から自社における水素利用を含め、他社に先んじた取り組みを続けていますが、なぜそこまで踏み込むのでしょう。
最初から水素事業を狙っていたわけではありません。いまから14~15年前、水素自動車用ステーションに使う冷却装置の開発依頼が来たのが出発点です。ただ、市場は小さく、10年以上販売していますが累計出荷台数は100台程度と、採算性は厳しいのが現状です。
当社としても一時は撤退を検討しましたが、経済産業省から「頑張って続けてほしい」と引き止められました。そこで、インフラ依存ではなく、自前で販売できる水素関連製品を育てようと考えました。
――採算性は厳しいとのことですが、水素事業がプラスになった面は。
これは事業を続けていくうちに分かったことですが、学生たちの水素に対する関心は非常に高く、国公立の大学からインターン希望が来るほどです。こうしたことからも、これは将来の投資として続けるべきだと判断しました。
また、私は在任中に水素が主力事業になるとは思っていません。将来に向け、次世代に会社の資産として残せればいい。無論、地球環境の保全という使命感もありますが、水素の利活用、研究開発の継続は企業の継承戦略のひとつとして考えています。
■国内市場の先行きと海外展開
――日本のマーケットは全体的に縮小傾向にありますが。海外展開はどう考えていますか。
中国は本来大きなマーケットですが、エアドライヤーなどは汎用化が進み価格競争が激しい。圧力容器規制もありますので、そのまま日本製を持ち込むのは難しい。ただ、精密空調はチャンスがあります。当社の幅広いラインナップから、中国市場に適した機種を段階的に現地生産へ切り替えています。
他方、アメリカにおいて日本製チラーはかなり競争力があります。本来は今秋にもテキサス州に拠点を作る予定でしたが、政治的な問題もあり先延ばしとなってしまいました。ただ、今後も北米拠点を開設する方向性でいます。
――インド市場はどうでしょう。
10年前に現地企業と合弁会社を設立しライセンス生産を開始しています。現地ではいま、印刷業界向け真空ポンプの需要が大きく、新たに真空ポンプ合弁会社を来年1月に設立予定です。インドは日本の高度成長期のような状況で、大きな潜在力があると感じています。
――日本と比べ、省エネ・脱炭素機器は海外で受け入れられやすいのでしょうか。
エネルギー価格が安い国も多いので、一概には言えませんが、中国も北京の空が青くなり、アメリカもインバーターの普及が進むなど、省エネや環境意識は確実に高まっています。提案次第ではまだまだ伸びしろがあると考えています。
■自社CO2排出量半減へ
――貴社はCO2排出量を大幅に削減する野心的な目標を掲げています。
基準年の2020年に当社は4300トンのCO2を排出していましたが、これを2030年までに半減するのが目標です。売上増により今年度の排出量は5000トンまで増える見込みですが、削減に向けては明確なロードマップを描いてます。
須坂インター工場の太陽光発電、水素燃料電池の導入やグリーン電力の活用、ろう付け工程における水素活用などを組み合わせると約1000トンの削減になります。本社工場も1メガ級ソーラーのカーポート型導入、空調の地中熱ヒートポンプへの転換、水素発電機の自社導入で段階的に取り組みを進めていきます。
――自社が脱炭素を念頭に置いた設備投資をする立場となって、改めて気づいたことは。
お客様が「もっと省エネにならないの?」「せめて3割下げて欲しい」と仰られる感覚がよく分かりました。設備を購入する際に「従来より5%削減できます」と言われても決め手にはなりませんから。だからこそ当社の製品開発も「3割削減」を前提にしないと、お選びいただけない時代になってきていると痛感しています。
(日本物流新聞2025年12月10日号掲載)