連載
伸和精工、宇宙・医療部品をAMで製作
- 投稿日時
- 2025/03/27 11:50
- 更新日時
- 2025/03/27 11:54
チタンの埋め込みデバイスもAMで
[小物部品のマシニング・旋削・放電加工およびAM事業]
山口県宇部市
東京大学発の宇宙ベンチャー・Pale Blueが開発した水蒸気を用いた小型衛星の推進機「水エンジン」。これを搭載した小型人工衛星が2023年に打ち上げられ、軌道上での噴射に成功した。水エンジンにはAM(積層造形)で作った金属製の流体部品が採用されていた。製作したのは山口県宇部市の伸和精工(柳井宏之社長)だ。

3Dプリンターで出力した金属製の歯科用部品(伸和精工提供)
使ったのはFFF方式(フィラメント材料を用いたAM)の金属3Dプリンター。SLS方式(粉末材料を用いたAM)の金属3Dプリンターより安く物を作れるが、造形物に隙間ができやすい。流体部品は密封性が求められ「かなり大変だった」(柳井社長)と振り返る。だが何度も作り直して無事、軌道上での噴射を成功させた。
金属の精密切削が得意な同社は、医療や半導体、宇宙、産業機械など様々な業界へ300㍉角までの小物部品を納める。最初に3Dプリンターを導入したのは13年で、大学の依頼で手術部品を作り始めたのが契機という。製作依頼はポンチ絵で届き、図面を起こして部品を削り出しても頻繁に作り直しに。それでは研究も滞るため黎明期だった3Dプリンターの導入に踏み切った。
その後に山口県で航空機産業への参入を目指した航空クラスターが立ち上がると、同社も参画することに。組織は航空宇宙クラスターへ名を変え、同社も18年にMarkforgedの炭素繊維の複合材料を造形できる3Dプリンターを導入し、東京大学などと宇宙分野の研究を重ねた。結局、炭素繊維の複合材で宇宙部品の製作は難しいとの結論に至ったが、追加で導入したFFF方式の金属3Dプリンターで冒頭の取り組みが叶った。
柳井社長は「宇宙産業は現状、予算も潤沢でなく定量的な需要が見込みづらい」とする。ただ「宇宙部品をAMで作ること自体は様々な会社が興味を持っている。現実になれば我々の知見が活かせる」と前を見据える。
■FFF×チタン
3Dプリンターは何に活かせるのか。柳井社長が目下、注力するのは医療分野だ。「体内に埋め込む様々なインプラントを3Dプリンターで作る取り組みを進めている」。試作結果は良好で、今年1月には医療機器製造業者の登録も受けた。
FFF方式の3Dプリンターは造形物の内部に空洞ができるが、柳井社長によると人工骨などのインプラントはこの特徴がプラスに働くという。「詳細は伏せるが組織が癒着しやすい」。医療分野で使われるチタンはFFF方式での造形が難しかったが、大手企業と実証を進めておりFFF方式でのチタンの造形も現実的になっている。
切削より簡単と思われがちなAMだが、機械や材料の価格、ランニングコスト、焼入れ等の手間を考えると切削より割高で「難しさも多い」そうだ。特に強度の担保が鬼門で、「ある形状で強度が満たせても形が違えば積層方向などの要素が違い同じ強度にならない」。ミルシートで強度を保証できる切削とは品質保証の手間が段違いだ。ただ同社はAMの黎明期から様々な企業や研究機関と共同実験を行っており、社外のつながりを利用し試験環境を用意できる点に優位性がある。
3Dプリンターは特に海外で進歩が著しく、高額な機械でなくとも高品質な造形が叶うようになってきた。今後もそうした最新設備を導入して造形品のコストを抑え、AM事業を多角的に展開する考えだ。
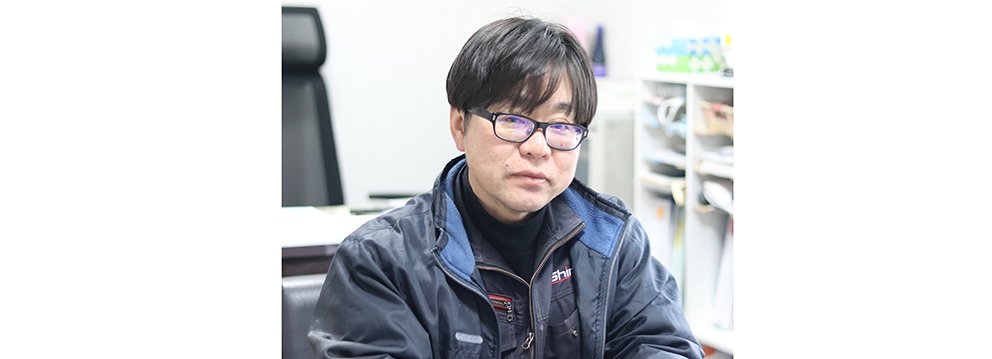
柳井宏之社長
(日本物流新聞2025年3月10日号掲載)





