連載
ファザーマシン2/Chapter57
- 投稿日時
- 2025/10/15 10:10
- 更新日時
- 2025/10/15 10:13
きさげ職人へのリスペクト
みなさん、こんにちは。工業系YouTubeチャンネル、なんとか重工のとんこつです。
今回は、「きさげ編その2」をお送りします!

三日月模様のきさげが施されたスペーサー
いよいよ、碌々スマートテクノロジーさんでの本格きさげ修行がスタート。修行に入る前にまず、海藤社長(現会長)の案内で、工場内を見学させていただきました。
最初に見せていただいたのが、工場内で厳重に管理されているマスター定盤。この定盤、なんと横幅2㍍ほどもある巨大サイズ。しかも1インチあたり25ポイントという非常に細かいきさげが施されており、その存在感に圧倒されました。
このマスター定盤は「3枚合わせ」という手法で製作されており、A・B・Cの3枚を互いに擦り合わせて精度を追い込んでいくもの。
今思えば、このサイズの定盤をひっくり返して擦り合わせるだけでも相当な作業だったに違いありません。
このマスター定盤を基に、子供定盤、孫定盤といった具合に転写しながら、現場で扱いやすいサイズへと“精度”を受け継いでいく。それはまるで人間の技能継承のようで、道具であるはずの定盤が、単なる『モノ』ではなく『存在』としてそこにあるように感じました。
ちなみに、この定盤が保管されている部屋は、23℃±0・5℃で温度管理された恒温室。工場の環境管理にも並々ならぬこだわりを感じます。
そして、きさげ修行がスタート。教えてくださるのは、碌々さんの中でもNo.1のきさげ職人・池ヶ谷さん。想像通りの寡黙な方でしたが、その手から繰り出されるきさげは本当に美しく、驚くほど安定していました。
■三日月形のきさげに苦戦
印象的だったのは、きさげを行う場所の考え方。私はきさげといえば摺動面(スライド面)だと思っていたのですが、碌々さんでは現在摺動面には行っていないとのこと。理由は、LMガイドの性能向上により必要がなくなったため。
では、どこにきさげをするのかというと、それは部品同士が接合する面。接合部にきさげを施すことで、長期間にわたって機械の精度が維持されるそうです。平面研削では実現できない精度を、手作業できさげによって実現しているというのだから本当に驚きです。
大きな面はそのままだと歪みが生じるため、きさげで面を細かく分割するようなイメージ。さらに驚いたのが、細かい部分の仕上げに使われる三日月型のきさげ。
この技法は碌々さんでしか行われておらず、手の動きも独特で、前に突きながら半回転捻るという複雑な動作。見ただけでは到底真似できるものではありませんでした…。
そして何より、会社全体から職人へのリスペクトを強く感じました。工場の環境整備はもちろん、一人に一台大きなキャビネットが支給されていたりと、ものづくりの根幹を支える人材を大切にする文化が根付いているのだと感じました。
動画公開後のコメント欄も、私ではなく(笑)会社や海藤社長(現会長)を称賛するコメントで溢れていました。でもそれだけ、視聴者の目にも「本物」が伝わった証拠だと思います。
この動画を通じて、「きさげって大変でなんかすごそう」という曖昧なイメージから、もっと具体的に『なぜ必要なのか』『何がすごいのか』が伝わったはずです。私自身も、非常に印象に残っている動画のひとつとなりました。
(日本物流新聞2025年10月10日号掲載)
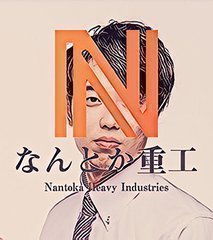
工業系YouTuber【なんとか重工】とんこつ
工業系YouTubeチャンネル【なんとか重工】を、相方のケロと2人で運営。旋盤やフライス、マシニングに溶接機、3Dプリンターなどを活用して自分たちが作りたいモノを作るチャンネル。登録者数は13.5万人(2025年10月15日現在)





